成功体験のある人間ほど失敗するのはなぜか?【中野剛志×適菜収】
「小林秀雄とは何か」中野剛志×適菜収 対談第4回(最終回)
なぜいま小林秀雄を読むべきなのか? 新刊『小林秀雄の政治学』(文春新書)を上梓した評論家・中野剛志氏と、『小林秀雄の警告 近代はなぜ暴走したのか?』(講談社+α新書)の著書もあり、小林を通して問題意識を共有する作家・適菜収氏との対談第4回(最終回)。われわれは新型コロナ禍において「未知の事態にどう処すべきなのか?」を問われているのである。小林秀雄にとって、それは「総力戦」という新しい現象だったが、人間は同じようなパターンで間違いを繰り返す。ふたりの対談から見えてくるのは、「人間の業」を理解するための「考えるヒント」である。
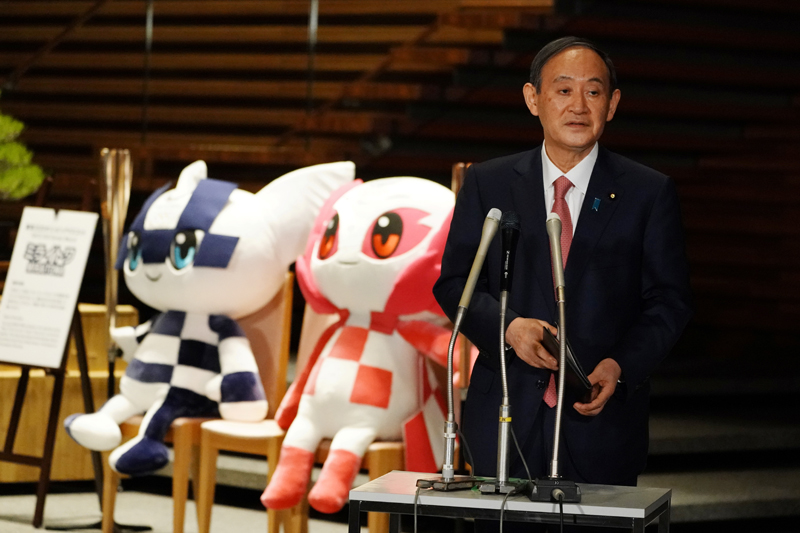
■二宮尊徳の「本の読み方」
中野:小林秀雄が二宮尊徳の話をするところがある。尊徳によると、書物を読むだけでは、言葉はつららみたいに固定的になっていて、そのままじゃ使えない。尊徳の言葉をそのまま引用すると、読む人の「胸の温気(うんき)」によって、言葉というつららを溶かして、水にして使う、つまり自分なりに解釈して応用しないとだめだというんですね。「本にこう書いてあったからこうなんだ」じゃなくて、本に書いてある趣旨を咀嚼して、自分のいるシチュエーションで活かさないとだめだと尊徳が言ってる。そう小林が書いているんです。まさにその通りだなと思います。
適菜さんの本(『小林秀雄の警告 近代はなぜ暴走したのか?』)も私の本もそうかもしれないけど、小林の言葉を自分たちで溶かしたわけですよ。これは、まさに理論と実践の関係と同じです。理論というものを、状況の違いを無視して、そのまま当てはめようとしてはいけないということです。
例えば、ヘーゲルでもマルクスでもケインズでも誰でもいいんだけれども、これを読んだ人が自分の胸の温気で溶かさないと、硬直的なヘーゲル主義、マルクス主義、ケインズ主義になってしまう。それは彼らの言葉を氷のまま持ってきているからであって、その言葉を溶かしてみることが大事です。すると、やっぱり古典っていうのは汲み尽くせないところがある。古典を溶かして今に活かすっていうのは、読み手側に温気がないとだめなんですけども、その温気というものこそが私たち自身の個性なんですよ。
適菜:溶かすというのは、対象が溶けるまで見るということだと思うんです。腑に落ちるというか。これも小林が言っていることですが、道を歩いていて、スミレの花があったとして「スミレの花だ」って思った瞬間にそこで見ることを止めてしまう。「スミレの花」という概念が入ってくるだけで、眼が動かなくなる。ヘーゲルでもマルクスでもケインズでも同じですね。よくある言い方ですが、マルクスはマルクス主義者ではなかった。彼らだって少し変わり者の生身の人間に過ぎなかったわけですから。

■イデオロギーはそのもの自体の本質を見えなくする
中野:そうです。ジョン・デューイの芸術論にも同じようなことが書いてあります。デューイは、「知覚(Perception)」と「再認(Recognition)」を分けている。適菜さんも『小林秀雄の警告』の中で書いていたけれど、美術館の絵についている解説とか、ラベルで「なんとか派」みたいなことが書いてあって、それを見て分かった気になるのが「再認」です。
例えば、向こうから誰か歩いてきた、「あ、○○が歩いてきた」「どうしよう、挨拶しようかしまいか」と迷う。でも「あ、○○だ」と思った瞬間が「再認」なのですが、「再認」した瞬間に、もうその人のことはこれ以上見ようとはしなくなる。これに対して「知覚」というものは、そうじゃない。例えば、向こうから歩いてきた〇〇の様子がいつもと違うことに気づいて、「あれ? 今日のあいつは、おかしいぞ? どうしたんだ?」とマジマジともう一回見るでしょう。これが、「知覚」です。その結果、その人のいつもと何が違うのかに気づくでしょう。
道端に咲くスミレの花を見て、「スミレの花」という名称だけ「再認」して何も感じずに通り過ぎるのか、見慣れたはずなのに、今まで気づかなかった新たな美しさを「知覚」してはっとするのか、という違いですね。
要するに、言葉による解説とか名札とかいったものは、対象そのものを見る際の邪魔になるんです。それがあることで、かえってそのものを見えなくしてしまう。これがまさにイデオロギーというものですね。例えば「ケインズ主義」というラベルや解説は、本当のケインズの姿を見せにくくするんです。そうじゃなくて、もう一回溶かすということをやらなければいけない。つまりケインズを読んで自分なりに解釈することをしないといけないということなんです。私が『小林秀雄の政治学』でやったことも、そういう解釈です。小林秀雄には、「文学者」「文芸批評家」といったラベルがあり、それが小林の姿をかえって見えにくくしています。もっと言えば、「小林秀雄」というラベルなのかもしれない。小林秀雄は「ああ、小林秀雄ね」で片付けられてしまっている。

適菜:ベルグソンに言わせれば、「芸術の目的は、実用に役立つ記号の群れや慣習的社会的に受容されている一般観念、すなわち実在をわたしたちに隠している一切のものを取り除き、わたしたちを実在そのものに直面させる以外のものではない」(『笑い』)のですが、それにさらにラベルを貼るのですから、なにやってんだという話ですね。
中野:昔、本当にカチンときたことがありました。私が小林秀雄の解釈をしたところ、それを聞いていた老人が「小林が何を言っているのかは分かったけど、私は、小林ではなく、君自身の意見が聞きたい」と偉そうに言ってきた。こういうことを言う人って、よくいるじゃないですか。「ならば、あんたも、自分で小林を解釈してみろ。そうしたら、俺と同じ解釈にはならないことが分かるから」と言いたかったですね。私の小林の解釈は、もちろん小林の言っていることを説明しているのですが、しかし、それは私自身のオリジナリティでもあるんだということです。
昔から手垢の付いたはずの古典、アリストテレスでもいいし、カントでもいいし、なんでもいいんですけれど、そういう古典を大勢の学者さんたちが飽きもせず何度も読んでは理解しようとしている。そして、次から次へとこれまでと違う解釈を出してくる。それは「氷を溶かす」ということをしているのでしょう。
結局「解釈なんかいいから、君の意見が聞きたい」という人は、オリジナリティというものを勘違いしているんですよ。そして、本を読むことの本当の愉しみを知らないのでしょう。
適菜:そうですね。過去に対する無知が近代人のオリジナリティという発想を生み出している。でも本当の意味でのオリジナリティは、オリジナリティなんて幻想だと気づくところからしか始まらない。これは、この対談の第3回でも述べましたが、型を極めたところに、型破りは成立するのであり、最初から型がなければ「型なし」というのと同じですね。小林が『モオツァルト』で書いたのもそういうことです。
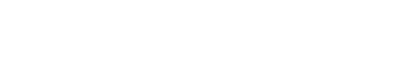




--204x300.jpg)








